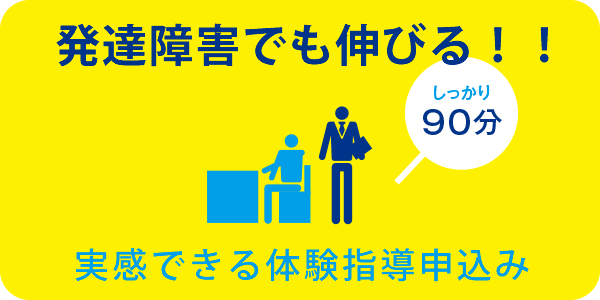間違い探し
ケアレスミス(計算ミス・漢字ミス)原因と防ぐ方法(発達障害)
母親「ウチの子はほんとケアレスミスが多くて」
プロ家庭教師のジャンプには、
- ASDゆえにこだわりが強くて見直しができない
- ADDゆえに不注意でミスを見落としてしまう
- LDゆえにミスをミスだと認識できない
といった特性ゆえの「ケアレスミス」をしてしまう生徒がたくさんいます。
そういった子供たちのお母様方からは頻繁に冒頭のような悩みを耳にします。
例)算数の途中計算での数字ミス
自分で書いた0と6を読み間違えしたり、筆算の位取りがズレたまま計算したり、7×9(シチク63)を(シク36)と頭の中で音韻の誤認識(「シチ」と「シ」)をしてしまったり、、
例)国語の漢字ミス
線が一本足りなかったり、似てるけどどこか違う字だったり、消しゴムで消したはずが完全に消えてなくてバツされたり、、、
例)国語の文章題
文章から抜き出せ、なのに自分流に変換してしまったり、
間違っているものを1つ選べ、なのに正しいものを選んでしまったり、
どうすれば、このようなケアレスミスを防ぐことができるのでしょうか。
その答えは、「何事も適切なトレーニングさえ積めば結果が出る」ということになります。
ジャンプの指導システムに「宿題の指示の仕方」「ノートの取り方」「暗記のコツ」「提出物の管理法」など、勉強のやり方全般でシステムがあります。それと同様に、ケアレスミスも「ケアレスミスをなくす指導法」というものがあります。
それはすなわち「自分の間違い部分を見つけるトレーニング」を毎日繰り返しすること。
ケアレスミスが起きる理由とトレーニング
生徒たちがなぜいつもいつもケアレスミスをしてしまうのか。
どうして間違いに気付けないのか。
いったいなぜ、「見直しをしなさい!」と口酸っぱく言っているのに毎回同じ過ちをするのか。
それは、子供たちは「多分合っている」と思って見直しするからです。自分の答えが間違っていると考えたくない思考がまず先にあって、きっと大丈夫なはずという淡い期待を抱きつつ見直しをするのです。「間違っていませんように」と祈りながら間違いを探そうとしても見つかるはずがないわけです。「間違いを見つけよう」など思っていないわけですから。
そしてもう一つ。子供たちは見直しをするとき、1回目と全く同じやり方で解こうとしがちです。同じやり方で解けば同じミスをするわけで、やってる本人がミスと気づくことはなかなか難しいと思います。
この意識のままで勉強をし続けることはとても危険です。(丸つけのケアレスミスについては河口先生のコラム「丸付つけだよ」も是非お読みください)
今後最優先に取り組むべきは、自分で自分のミスを発見できるようになるためのトレーニング。1行程ごとに部分分解して、符号、数字、式の形など調べる項目ごとにチェックしていく訓練を積ませることです。
それさえ徹底していけば、「あ、違う!」と解いてる途中で気付けるようになります。
また、特性あるゆえどうしても見直しをやらない子供もいます。その場合、ケアレスミスが起きなければ見直さなくていい、という発想に持っていく必要があります。なぜケアレスミスが起きるかというと、その原因の一つに「ミスに気づけないくらい脳の容量をかなり限界まで他の領域(感情)に使っている」というものが挙げられます。(早く解きたい!早く終わらせたい!早く後ろの応用問題解かなきゃ!こんなの簡単!こんなの余裕!こんなの知ってるしみんな出来る問題だからゆっくり丁寧にやるなんてよくない!!!)といった感情です。
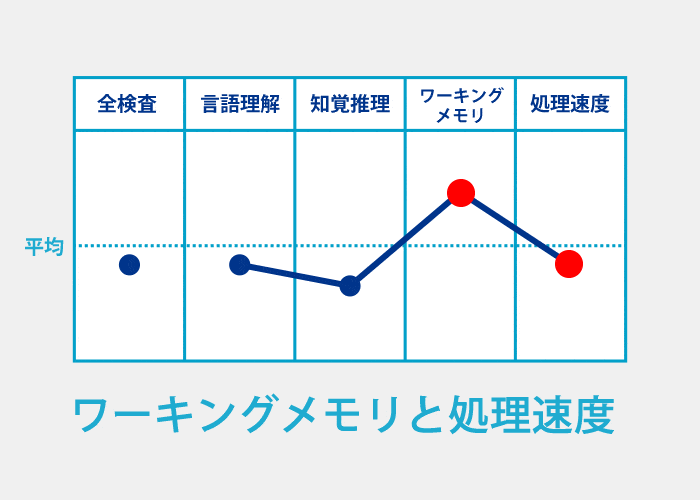
それらを考えないようにすることはほぼ不可能です。ではどうすればいいかといいますと、それらを考えていても同時にミスをしないだけの処理能力をつけさせていくしかありません。WISC(ウイスク)の4つの項目のうちの「処理速度」と「ワーキングメモリ」を鍛えていくことで、同時処理能力が高まりミスしないようになっていくわけです。
「あ!まさにウチの子の事だ!」と思われたお母様、一度、私たちプロ家庭教師の体験授業を受けさせてみてください。
きっと、お子様に合った適切な指導法が見つかるはずです。
「発達障害でも伸びる!」体験授業
プロ家庭教師のジャンプには発達障害(学習障害やADHD、自閉スペクトラムなど)を抱えた生徒さんの指導に豊富な経験があります。
「ケアレスミスが多い」「学校の授業についていけない」などお悩みの方は是非「体験授業」をお試しください。
「算数が苦手」を克服!
ジャンプには発達障害や軽度知的障害を抱えた生徒さんの「算数の学力力アップ」に豊富な経験があります。算数が苦手なお子様の中学受験にも対応しています。
必見! 発達障害ブログ
- 発達障害と特別支援学級(高田先生)
- 発達障害と中学受験(高田先生)
- 中学受験「偏差値50」2科目か4科目か(高田先生)
- 中学受験「偏差値40台」応用問題(仲間先生)
- 中学受験『算数の計算ミスは致命傷になる』(高田先生)
- 発達障害と漢字の覚え方(今泉先生)
- 発達障害と英単語の覚え方(高田先生)
- 勉強ができないのは発達障害のせい?(尾崎先生)
- 発達障害とWISC知能検査(今泉先生)
- ワーキングメモリと勉強(高田先生)
- 発達障害と志望校選び(鎌田先生)
- 発達障害とカラーテスト(深澤先生)
- 発達障害と白黒思考(岡田先生)
- 発達障害と小学生の算数(儘田先生)
- 発達障害と小テスト(山中先生)
- 発達障害と親の言葉(高野先生)
- 発達障害と不登校(島田先生)
- パズルで簡単!楽しく身につく漢字学習指導法(鎌田先生)
- 発達障害と漢字の必要性(高田先生)
- 発達障害とケアレスミス(儘田先生)
- 漢字を覚えられないのはなぜ?(田中先生)