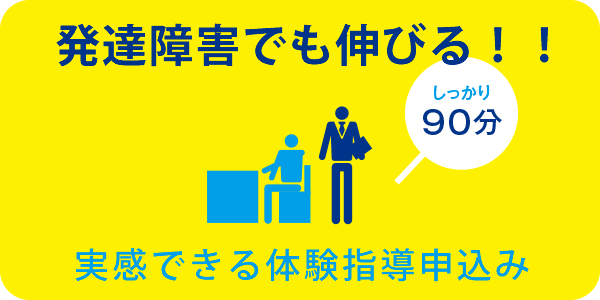学びなおし
「勉強が苦手」の原因は発達障害か?(発達障害)
- 「勉強が苦手」の原因は発達障害か?
- 発達障害でも伸びる条件
- 「学びなおし」の環境を用意する
- 精神的なサポート
- 教師の一言が子供を深く傷つける
- 想いへの配慮
- 発達障害関連の人気コラム一覧
- 「発達障害でも伸びる!」を実感できる体験授業
「勉強が苦手」の原因は発達障害?
プロ家庭教師のジャンプには発達障害やその周辺にいる子供たちがたくさんいます。
- [LD]学習障害・[ADHD]注意欠陥多動性障害・[ASD]自閉スペクトラムなど脳の情報処理システムや伝達手段において生まれつきの特性を持つ子供たち
- 単語や漢字が覚えられない子供たち
- 療育センターや小児科などで、WISCや田中ビネー、K式といった知能検査、発達検査で視覚的認知、聴覚的認知、ワーキングメモリー、処理速度などにおいて顕著な有意差や数値の特徴(得意不得意分野がハッキリしている)が見られるといったアセスメントを受けた子供たち
- 診断名がつかないグレーゾーン域にある子供たち
- 愛着障害など後天的な環境要因により発達障害に似た症状がある子供たち
- 自立性調節障害、場面緘黙、軽度知的障害、協調性運動障害、感覚過敏、癇癪を起こしやすい、といった状況下にいる子供たち
- ユーチューブやゲーム依存、スマホ依存の子供たち
- 通級、特別支援学級に在籍していたり放課後デイサービスに通う子供たち
- ストラテラ、コンサータ、エピリファイやインチュニブといった薬を服用している子供たち
私も含めてジャンプの教師陣(ジャンプの教師は全員がジャンプで正社員として家庭教師をしています)はそういったなんらかの特性を抱えて勉強面で困っている子供たちを幼児から高校生に至るまでたくさん現場で指導しているわけですが、指導をしていてそういう生徒たちと日々完全マンツーマンで接するなかで普段から想うことがあります。
それは、
という疑問です。
もしかしたら、大人数がダメだったり、教師との相性(教え方も含め)だったり、そうした外的な要因も大きく影響しているのではないか?
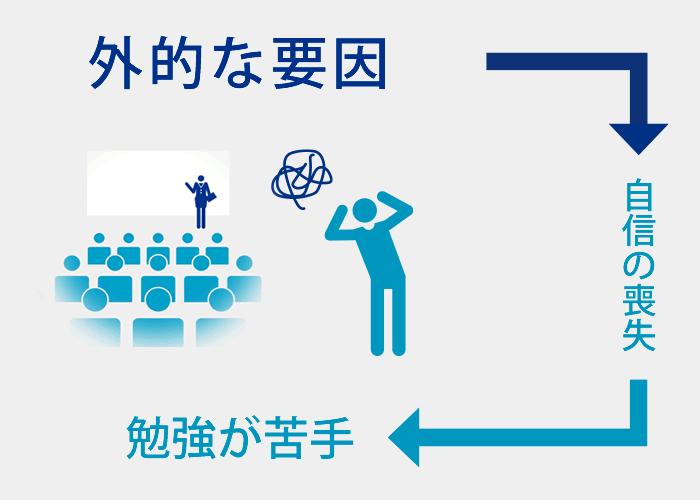
なぜそう想い至るのかというと、自閉スペクトラム(ASD)・注意欠陥・多動性障害(ADHD)・学習障害(LD)など、ひとりひとり抱える特性や得意不得意分野も異なるといえど、どの子供にも共通しているのが、
- 教えればどんな特性を持っていようと、年齢や偏差値に関係なく、その子に合ったオーダーメイドのプラン作成や教え方をすれば着実に出来ることが増えていっている
- できることが増えて、それを認めてあげて、褒めて伸ばしていけば勉強することを前向きに考えられるようになる
- 前向きになれば学習習慣もついてくる
と生徒たちの様子をみてきて実感しているからです。
これは私自身が今まで何十人という「学習障害の可能性がある子供たち」を教えてきた経験からですが、重度の学習障害の場合ですと、例えば字が常に無秩序に動いて見えて読むことすらできなかったり、形として字を認識できなかったりする子供もいます。しかし大抵の子供達は軽度の学習障害と診断されていたり、親がもしかしたら学習障害かも?と考えているだけで本当は学習障害に近い症状、学習障害に見える症状であって、アプローチの仕方一つでよくなっていくこともたくさんあるのです。書くことはすぐに好きにはならなくても漢字というものに対しての抵抗感はなくなっていってくれたりするわけです。
また、ADHDやADDと診断され、単語や漢字を覚えてもすぐに忘れてしまう子供たちでも、その子に合った忘れない覚え方や復習法を見つけていけば、長く覚えていられるようにもなってくれますし、60分や90分の長い時間集中もできるようになってくれます。
だからこそ、私は親御さまに「発達障害の特性に合わせて指導をすることも大切ですが、発達障害の特性関係なく、適切な指導方法、扱う問題レベルや指示の仕方、適切な量や適切な反復メニューを指導する側が持って向き合えば、どんな子供でもその子なりに階段を一つずつ登っていくことができます」と言います。
発達障害でも伸びる条件
- 適切な指導方法
- 扱う問題レベルや指示の仕方
- 適切な量や反復メニュー
もちろん私自身最初から、つまり大学時代家庭教師のアルバイトをしていた当時からそのような考えを持っていたわけではありません。正直申し上げると、当時は『発達障害』という言葉自体むしろよくわかっていませんでした。
しかし正社員として、プロの家庭教師として、ジャンプで働くようになってから「発達障害」というものへの理解が大きく変わりました。それまではなんとなく、知的障害は知能検査の数値で軽度、中度、重度と判別され手帳も交付されるから、発達障害もWISCなどの検査の数値で障害の判定がされるのだろう、と考えていました。また、発達障害の子供はみんな小学校も中学校も特別支援学級に在籍しているのだろうとも思っていました。そういった発達障害への認識が全然間違っているとわかったのはジャンプに入社してからです。WISCの数値と発達障害の診断は別物ですし、普通学級に在籍している発達障害の子供もたくさんいるわけです。アルバイトや登録制の家庭教師だとわからない部分、見えない部分が正社員家庭教師として採用されてからわかるようになり見えるようになりました。
そして結果にこだわる指導システムを現場で実践できるようになってから、少しずつ「発達障害でも伸びる!」という考えを持てるようになってきました。なぜなら、自分が教えてきた生徒が、ほぼみんな、できるようになっていったからです。『できるようになる』といっても『数の概念がわかるようになる』『文章題がわかるようになる』『単語が覚えられるようになる』『学習習慣がついた』など、できるようになったところはみんな違います。けれど、『できるようになっていく』ことで自分に対し自信を持ち、自己肯定感が高まっていったことは間違いありません。
冒頭の
に対する私の今の答えは、「発達障害とは別のことがきっかけで勉強が苦手になっている子供がたくさん世の中にはいる。別のきっかけの大半は集団授業での勉強の遅れなど外的要因、つまり内面的なものではないことが多く、きちんとした【学びなおし】の環境を用意してあげれば必ず伸びるはず」ということです。(外的要因については、例えば現在の小学生はみんな大変、ということが儘田先生コラム『現代の小学生の算数カリキュラム』に書かれています。)
- 集団授業での勉強の遅れ
- 自信を喪失
- 勉強が苦手
- 【学びなおし】の環境(=ジャンプの指導システムの存在)
- 自信を回復
- 発達障害でも伸びる!
正社員家庭教師の精神的なサポート
また、精神的なサポートも同じくらい重要だとも認識しています。
話が変わりますが、発達障害やグレーゾーンの子供、特に小学生と中学生を何人も担当してきましたが、生徒さんと親しくなってくると、こんな質問をされることがあります。
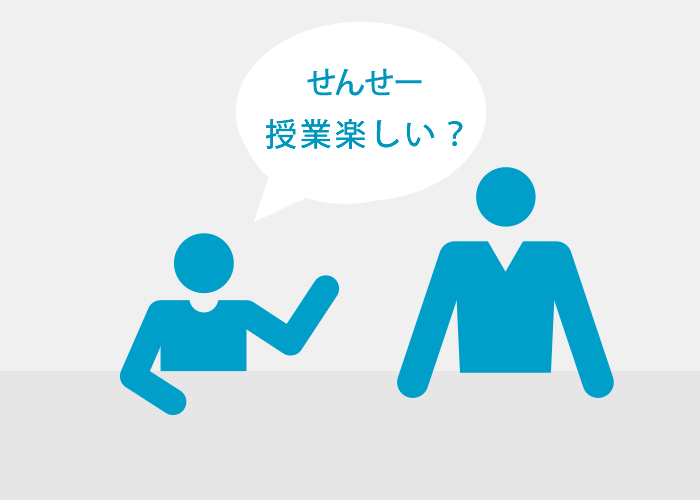
「せんせー、せんせーって授業やってて楽しいの?」
私はいつもこう答えます。
「楽しいに決まってんじゃん!楽しくなかったら、仕事にはしてないよ!!〜君との授業は特に楽しいよ!」
こう答えると、生徒さんは少し恥ずかしそうに、はにかんだ笑顔を見せてくれます。親御さんにそういったやりとりの話を報告したりする時にわかるのですが、大体この質問があった時はどの生徒さんの場合も、学校の先生等から
- 「キミは、本当に手がかかる」
- 「他の生徒の妨害をしている」
などといった子供の感受性をないがしろにするような傷つく発言を受けた直後だったりします。
「せんせーって授業やってて楽しいの?」
質問の意図は、「先生が仕事としての家庭教師を楽しいと感じているか」を知りたいのではなく、「先生は自分のような手がかかる(と周りから言われている)人間に勉強を教えることをどう思っているのか、本当は面倒くさいと思っているのではないか」を確認したいのです。
子供にとって学校の先生はとても影響力のある大人です。そんな大人から「手がかかる、妨害をする生徒」というレッテルを貼られると、大抵の子供は劣等感や疎外感を持ってしまいます。教師側が放つ些細な一言が子供を深く傷つけ悩ませるのです。そこからくる自己肯定感の喪失、自分への期待の低下がそういった「自分はどう思われているか」の確認に表れているわけです。
発達障害という症状が世間一般に認識されるようになって数年以上経ちますが、マイナスのイメージだけが一人歩きしているように思えます。発達障害やその周辺にいる子供と日々向き合う現場の教師でさえ、今なお発達障害への理解が乏しく、偏見や誤認識で誤った発言や行動をする人もいます。
どんな教師、どんな担任に当たるかは運に左右されるとしか言いようがありませんが、運悪くそのような教師にあたってしまうと最悪不登校になってしまう可能性もあるわけです。実際そうなってしまった子供たちを何人も見てきた立場としては、子供の何気ない質問や興味の裏に隠された『想い』に気付いてあげる、配慮してあげることがとても大事だと思います。
何かがきっかけで勉強への自信をなくしてしまったり、対人関係でつまずいてしまったり、、、
けれどまた何かがきっかけで再び勉強への自信を取り戻したり、他者とうまく関われるようになったりもすることだってあるわけです。だから周りの私たち大人がまずは子供の『想い』を理解してあげるべきです。
勉強へのやる気がない
やる気がない子なんていません。やる気はあるけど、もっと他の楽しいことに興味があるのでやる気がないように見えるだけかもしれません。
集中力がない
集中力がないのでなく、問題がわからない、だから出来なくて困っているのかもしれません。誰だって、一人で考えても解けない問題は、「集中してやりなさい」と言われても集中しようがありません。だって解けないわけですから。
単語を覚えられない
覚えられないのではなく、もしかしたら覚え方を知らないだけかもしれません。「覚える」とは、いったいどうやれば良いのか。そこから丁寧に教えてさえあげれば、みるみる成長していくかもしれません。
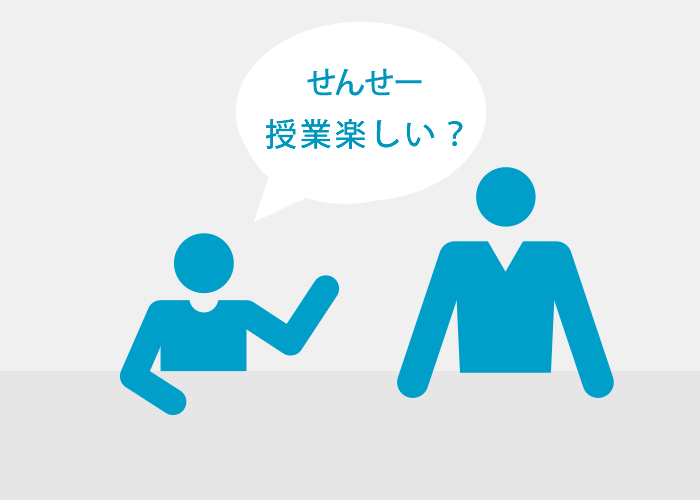
「せんせー、せんせーって授業やってて楽しいの?」
本当に純粋に疑問だったのかもしれませんね。『手がかかる』はずの自分と授業をしているのに、私が笑いながら楽しく授業をしている姿が。
けれど実は本当に楽しんでいるんです。もしかしたら、生徒以上に楽しんで授業をしているかもしれません。なぜなら自分が楽しめない授業を、生徒さんが楽しめるはずがありませんから。勉強には環境も大事だと言いますが、その入り口は生徒さん自身が『楽しい!』と思える勉強の場を提供してあげることだと思います。自分との授業がその入り口になってくれたら、家庭教師としてこれ以上嬉しいことはないかもしれません。
生徒さんや保護者の方から「プロ家庭教師のジャンプに入会して、先生と出会えて本当に良かった」と言っていただけることは大変嬉しいですが、むしろ自分のほうこそ「僕の生徒として出会ってくれて本当にありがとう」といつも心で思っています。
一番はじめに「体験授業」(「無料体験」や「体験指導」ともいいます)があってそこで自分も初めて生徒さんと会って、お互い自己紹介したり雑談も交えたりしながら授業もするのですが、実はいまでも毎回とっても緊張しているのです。なぜなら僕の人生の何分の1かをこれからしばらく共有していくことになる大切な子供との最初の出会いだからです。
- どのくらいこだわりがあるのかな
- 感情のコントロールはどうだろうか
- 短期記憶や作業記憶はどれくらいかな
- 耳より目からの情報のほうが理解しやすいならタブレット教材も積極的に活用してみるか
といった特性部分も勿論気にはなりますし、把握してあげれるよう努めますが、むしろ
- お、こういう表現だと笑ってくれるのか!
- あ、目を見て話すのが苦手なんだな
- なるほど、ゲームの話やYouTubeの話題だと食いつきがいいのか
- ふむふむ、将棋と卓球が好きなのか
といった性格的な部分を知ってあげて落ち着ける環境や楽しく過ごせる雰囲気、わかりやすいと思ってもらえる授業を作ってあげることのほうこそ大切にしています。
正社員だからずっと一人の生徒さんを担当していける。生徒さんからしても、ずっと同じ先生が自分をみてくれる。そこに安心感、信頼といったものが生まれるのだと思いますが、同時に僕たちプロ家庭教師には責任感も生まれます。
責任があるからこそ、真剣に向き合い、なんとかしてあげたいと思える。そのために、目の前の一人の生徒さんの笑顔や成長のために準備をしたり、教材を創ったり、指導法を考えたりできる。喜んでもらえるし、自分も成長できる。だから仕事が楽しい。だからやめられない。だから誇りを持って仕事ができる。だから一人でも多くの発達障害や悩みを抱える子供に知ってもらいたい。出会ってあげたい、いや、出会うべきだ。僕たちプロ家庭教師ジャンプの先生達と。
僕たちは誰よりも子供の可能性を信じて、ひたむきに前を向いて、走り続けていきたい。
以上、独り言をつぶやいてみました。
ご清聴、どうもありがとうございました。
発達障害関連コラム
- 『発達障害と中学受験』(高田先生)
- 『発達障害と特別支援学級』(高田先生)
- 『発達障害とWISC(知能検査)』(今泉先生)
- 『発達障害と志望校選び』(鎌田先生)
- 『発達障害とカラーテスト』(深澤先生)
- 『発達障害と文章題』(岡部先生)
- 『発達障害と小テスト』(山中先生)
- 『発達障害と親の言葉』(高野先生)
- 『発達障害と不登校』(島田先生)
「発達障害でも伸びる!」を
実感できる社員による体験授業
プロ家庭教師のジャンプは株式会社ジャンプジャパンで正社員として働くスタッフが指導を担当しています。アルバイトの家庭教師とは違う指導クオリティがそこにはあり、発達障害(学習障害やADHD、自閉スペクトラムなど)に対応できる経験豊富な教師だけが在籍しています。
WISCなどの検査を受けて初めて子供が今まで実は困っていたんだとお知りになった保護者様。
なんか少し他の子と違うな、どうして字が書けないのかな、覚えられないのかな、覚えてもすぐ忘れるのかな、数の概念がないのかな、ケアレスミスが多いのかな、と漠然と感じていたことが数値として表れ、「あー、こういう脳の特性があったからなんだ」と判明して、「じゃあこの子に合う、この子の、特性を理解してくれる塾や家庭教師はないかな」と一生懸命探され、「塾も家庭教師も結局はどこも直接指導してくれるのはアルバイトか、、、」と打ちひしがれ、ようやく【正社員による発達障害専門の家庭教師会社】、つまりプロ家庭教師のジャンプにたどり着かれた保護者様。
私達はそんな保護者様やお子様の困りごとを真摯に受け止め、寄り添いながらお子様に合うベストな学者方法を見つけていきます。
そういった発達障害やグレーゾーンの子供を教えたいという想いでこの仕事を本業として選んだ社員が、お子様の担当教師としてずっと責任もってみていきます。
まずは最初の体験を受けてみてください。
体験でその社員教師を気に入っていただければ、そのまま引き続きずっとその社員教師が指導を担当いたします。この「正社員による指導」が私達プロ家庭教師のジャンプの1番の強みです。
最後に簡易的ではございますが、よくいただく質問にお答えします。
費用は以下の3点のみです。教材などは毎回無料で用意いたします。
①入会金
33000円(税込)
②月謝(小1〜中2の場合)
月4コマ35200円(税込)
月8コマ52800円(税込)
指導科目は応相談可能です。
③交通費
最寄りの事務所からの公共機関代
※詳しい学年ごとの料金や会社概要などもホームページに載せてありますので是非ご覧ください。
また、指導の振替や途中での教師交代、途中のコース(回数や時間、科目)の変更なども柔軟に対応しております。
必見! 発達障害ブログ
- 発達障害と特別支援学級(高田先生)
- 発達障害と中学受験(高田先生)
- 中学受験「偏差値50」2科目か4科目か(高田先生)
- 中学受験「偏差値40台」応用問題(仲間先生)
- 中学受験『算数の計算ミスは致命傷になる』(高田先生)
- 発達障害と漢字の覚え方(今泉先生)
- 発達障害と英単語の覚え方(高田先生)
- 勉強ができないのは発達障害のせい?(尾崎先生)
- 発達障害とWISC知能検査(今泉先生)
- ワーキングメモリと勉強(高田先生)
- 発達障害と志望校選び(鎌田先生)
- 発達障害とカラーテスト(深澤先生)
- 発達障害と白黒思考(岡田先生)
- 発達障害と小学生の算数(儘田先生)
- 発達障害と小テスト(山中先生)
- 発達障害と親の言葉(高野先生)
- 発達障害と不登校(島田先生)
- パズルで簡単!楽しく身につく漢字学習指導法(鎌田先生)
- 発達障害と漢字の必要性(高田先生)
- 発達障害とケアレスミス(儘田先生)
- 漢字を覚えられないのはなぜ?(田中先生)