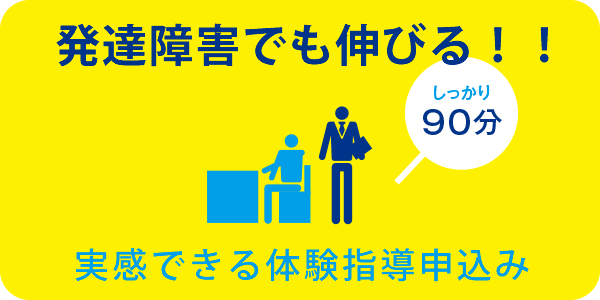発達障害
得意と不得意(発達障害)
発達障害に対して「得意・不得意に大きな差がある」という見方があります。
得意なこと、興味があることは能動的に行動できるが、不得意なことに関しては、得意なことと比較して受動的かつ考えて行動することに大きな差が生じます。生徒の得意・不得意を理解した上で勉強につなげていくことが勉強の成果向上へとなっていきます。
少し事例を挙げて説明します。
たとえば、得意な科目は数学というケース。
数学といっても、単純計算・段階を重ねる計算・文章題・図形・図形の証明と分野は幅広く存在します。
この中で計算が得意な生徒は計算問題はすらすら解くことができますが、段階を重ねる計算は考える作業を要するため、苦手な分野と変わり、できなくなるケースがあります。
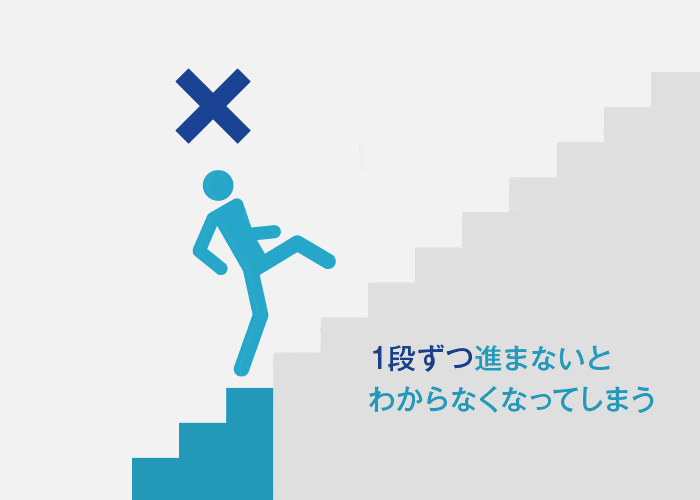
ここで、数学は不得意科目なのだと決めつけてはいけません。計算ができるのだから、段階をパターン化しパターン練習をして、計算の手順を丁寧に踏んでいけば必ず解けるようになり、パターンを思い出す練習が考える練習となり不得意が得意へと変わります。
この得意をいかすことにより、理科の計算も得意分野となります。得意なことを見つけることがまずは勉強に向き合う大きな一歩です。そこからスモールステップで学習をすすめていけばよいのです。
得意なことなんだろう?
先生たちと一緒に探してみませんか?
「発達障害でもできる!!」体験授業
プロ家庭教師のジャンプには発達障害(学習障害やADHD、自閉スペクトラムなど)を抱えた生徒さんの指導に豊富な経験があります。
スモールステップを取り入れたジャンプ式の指導を体験してみませんか?
必見! 発達障害ブログ
- 発達障害と特別支援学級(高田先生)
- 発達障害と中学受験(高田先生)
- 中学受験「偏差値50」2科目か4科目か(高田先生)
- 中学受験「偏差値40台」応用問題(仲間先生)
- 中学受験『算数の計算ミスは致命傷になる』(高田先生)
- 発達障害と漢字の覚え方(今泉先生)
- 発達障害と英単語の覚え方(高田先生)
- 勉強ができないのは発達障害のせい?(尾崎先生)
- 発達障害とWISC知能検査(今泉先生)
- ワーキングメモリと勉強(高田先生)
- 発達障害と志望校選び(鎌田先生)
- 発達障害とカラーテスト(深澤先生)
- 発達障害と白黒思考(岡田先生)
- 発達障害と小学生の算数(儘田先生)
- 発達障害と小テスト(山中先生)
- 発達障害と親の言葉(高野先生)
- 発達障害と不登校(島田先生)
- パズルで簡単!楽しく身につく漢字学習指導法(鎌田先生)
- 発達障害と漢字の必要性(高田先生)
- 発達障害とケアレスミス(儘田先生)
- 漢字を覚えられないのはなぜ?(田中先生)